渇水で流れる水が無くなった川、水無川。バイクで走りながらその干上(ひあ)がった白い石ころだらけの川底を見るとガッカリする。岩手県・国道283号線。その国道沿いを流れる「甲子(かつし)川」。仙人峠を源とし、釜石湾に注ぐ20数キロほどの二級河川。アイキャッチ画像は、水量不足から川底丸見えの「甲子川」。上中島地区と源太沢地区を結ぶ新開橋から上流部を撮影。「甲子川」は、戦前から戦後、高度経済成長期にかけて日本で唯一、鉄鉱石を掘り出し、鉄を作り出した鉄の街・釜石の最盛期を支えただけでなく、魚が湧きに沸く漁協権の無い河川としてひときわ異彩を放った水量豊富な名河川だった。渇水の原因は、気候温暖化だろう。「世界的に見ても気候温暖化の影響がもっとも顕著な場所、三陸地方」とネットを検索すると出ていた。海水温が2023年から例年より6度ほど高く、異常な状態が続いている。今年の8月は降水量は僅か25.5mmとゼロに等しい。気候温暖化の影響は、海だけでなく陸地にもその影響が出ている。

旧釜石製鉄所は、大橋鉱山から採掘される鉄鉱石を原料とし戦前から鉄鉱石を溶かす高炉2基を中心とした銑鋼一貫製鉄所。製鉄は 巨大な水資源依存型産業。水の利用の内訳(おおよそ)は、設備冷却:60〜70%、圧延材冷却:20〜30%、集塵・洗浄・その他:10%程度で使われ、冷却などに使われた水は再利用され排水される。製鉄所全体(高炉・転炉・連続鋳造・圧延を含む)、大規模製鉄所では 1日で数十万〜100万トン超 の水を取水・年間にすると 数億トン規模 の水を利用するとされている(チャットGPTで検索)。製鉄を支えた「甲子川」がいかに水量豊かな川であったか、再認識させられる。
その「甲子川」。日本では珍しく、川に漁業権がない。故・鈴木東民さんが市長の頃「市民の川に漁業権を設定するのはおかしい」と漁業権が設定されなかったという(この部分は何かで読んだ記憶で不確かです)。だから、入漁料を払う、遊漁券を購入する必要が今でもない(ただ、昔、アユは鑑札という遊漁券の購入の必要があった)。釣りの対象魚種は豊富で、淡水域ではアブラハヤ、ウグイ、アカハラ(ウグイの婚姻色が赤く出た物)、イワナ、アメマス(イワナの降海型)、ヤマメ、サクラマス(ヤマメの降海型)、鮭(サケ、すいません。釣っていけない魚でした)、アユ、ウナギ。たまに、カラフトマスも釣れた。汽水域ではハゼ、ヌマガレイなど。撮影場所の新開橋は、上中島地区と源太沢地区を結ぶ橋。右手から沢が流れこみ、春先に海から遡上してくる40㎝クラスのアメマス(雨鱒)が必ず釣りあげられる好ポイントであった。甲子川にはこのように良く釣れる有名な場所があり、市街地を流れる川の常として、毎日のように釣り人が釣り竿を垂れる。が、その場所が釣れなくなるということは無かった。増水など水量に変化があると新しい魚が入り、子供でも大人顔負けの釣果を記録することもあった。5月には鮎の稚魚が堰堤を大挙して駆け上がり、それを追ってウミネコが海から川沿いを飛んできた。9月に入ると鮭の遡上が始まり、県条例で釣ってはいけないのだが、アメマス、イワナ、ヤマメ狙いで投げるルアー(疑似餌)に鮭(サケ)がかかり、カーボンロッドを満月のように丸く締めこまれる光景がよく見られた。10月に入ると旧小佐野中学校沿い(現・小佐野小学校沿い)のトロ瀬に産卵を終え、力尽き、体が白く傷つき、力なく泳ぎ、体を横たえ死を迎えようとしている大量の鮭(サケ)が集まった。冷たい水面下であえぐ、その鮭(サケ)の姿は、季節の深まりと相まって生きる事の意味を老若男女問わず問いかけているかのようだった。
製鉄所があったため釜石は日本有数の公害の街でもあった。1976年、4月。公害の街・釜石の大渡川(甲子川の最下流部)に鮭(サケ)が再び遡上する姿が見られた。製鉄所から排出水などの影響で鮭(サケ)の遡上は、製鉄所の隆盛と相反するように途切れたようだが、1965年から始まった製鉄所の縮小とともに復活したようだ。しかし、二酸化炭素の排出量の増加が気候変動をもたらし、その影響で海水温が上昇、また、降雨量が減少して川の水量、水温が変化、鮭(サケ)の遡上に影響を与えているのは文明の皮肉というものだろう。僕は、甲子川にそそぐ小さな支流、小川川の川岸から堤防を挟み十数mほど離れた川沿いに住んでいる。この川にも鮭(サケ)の遡上がかつてあった。最後に遡上した鮭(サケ)ー1匹だけだったがー を見たのは、2018年頃だったと記憶している。残念な事だか、自分が生きている間に鮭(サケ)の遡上をみることは無いだろう…。

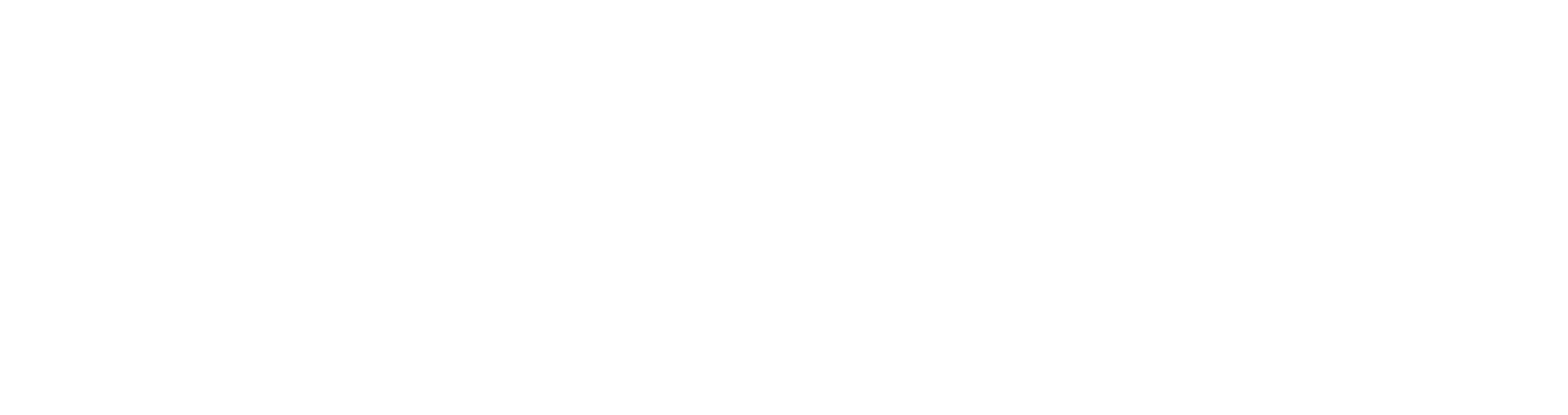



コメント